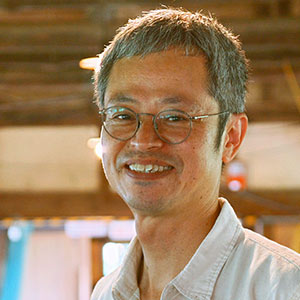酪農の赤字をキャンプで相殺!? 持続可能なひとつのモデル

この記事の登場人物
川上鉄太郎株式会社Chicabi /千葉ウシノヒロバ 代表
 " alt="">
" alt="">
千葉ウシノヒロバ代表、川上鉄太郎さんは、千葉市が50年以上に渡り行なってきた乳牛の預託事業を廃止することを決めた2019年3月、その事業と歴史を引き継ぐ後継者として手を挙げ、キャンプ場と育成牧場が共存する新たな観光スポットとして、千葉ウシノヒロバを2020年4月に開園させました。
もくじ
経営コンサルタントであり、デザインの力で企業や行政が抱える問題を解決に導いてきたデザインファーム、Chicabiを率いる川上さんですが、酪農はまったくの初心者。赤字必死のこの事業をなぜ受け継ごうと思ったのか。開園から5年、今感じていることや今後の展望をお聞きしました。
●プロフィール
川上鉄太郎(株式会社Chicabi /千葉ウシノヒロバ 代表)
1985年生まれ。慶應義塾大学法学部卒業、英国バーミンガム大学ビジネススクール修士課程修了。帰国後、株式会社野村総合研究所の経営コンサルタントとして、消費財B2C企業中心に経営戦略、マーケティング戦略を担当。7つの事業立ち上げに携わり、現在は株式会社Chicabi、千葉牧場、BRAND AND CONSULTING AGENCY代表取締役社長、OCEAN TRICO COO等を務める
赤字の預託を観光事業と合わせて成立させる
2020年、千葉市から預託事業を引き継ぎ、開園された千葉ウシノヒロバですが、預託事業に関しては完全に赤字経営。最初からビジネスモデルが破綻している事業に手を挙げるのは、なかなかの変わり者。そこには一体どんな思いがあったのでしょうか。
「たしかに、変わり者ですよね。」と笑う川上さん。
「始めるにあたり、一部補助金を出してはもらっていますが、4億円ほどの予算がかかっています。しかもこれまでは市の税金で賄われてきた赤字事業ですから、経営目線で言えば誰もしない、本当に考えられない判断だと思います。」
それでも乗り出したのは、「預託事業をキャンプなどの観光事業で補填することで回していくことができるのではないかと考えたから。」
自分が手を挙げなければ千葉市の預託の歴史は、きっとここで途絶えてしまう。自分がやる意味があるのであればやってみようと思ったのが始まりだそうです。
キャンプブームで黒字化実現。ブームが終焉した今、経営者としての手腕が試される
開園から5年、経営を続ける中で、ぶつかる壁などはあるのでしょうか。今感じていることについて尋ねると、「想像以上に大変」と、なかなか思い通りにはいかない様子。
「預託の牛を集めてキャンプ事業との二軸でいけば、なんとか預託事業をカバーして黒字化できるだろうと考えていましたが、実際は預託の牛が最初に聞いていた予定数集まらないということが起こり、立ち上げにあたっても苦労が多くありました。」
ただ、開始から2年目あたりまではコロナ禍から始まったキャンプブームの最中。
「コロナ禍のキャンプブームもあり、ありがたいことに盛況で、3年目には初めて会社全体で黒字化することができました。破綻していた預託のビジネスモデルを観光でカバーすることができると証明することができたんです。ただ、キャンプって、トレンドだったんですよね。」
バブルの熱が冷めて、キャンプ業界自体が傾いてしまった。キャンプ事業の売り上げを担保するためには、今後はブームに頼らない設計や価値提供が必要となってきます。まさに事業経営者としての手腕が試される時です。
「元々がバブルだっただけと考えると、ブームにかかわらずキャンプが好きな方や好きになる可能性のある方々にしっかりと価値を届けられれば、回るはずです。ですが、僕らが始めてから飼料が高騰してコストが上がり、廃業していく酪農家さんも多く出てきて、預託の運営に影響が出ていることも事実です。千葉市とは昨年から1年近く話し合いを続けて、今年2月から、預託料を上げていただきました。」と川上さん。
新たな取り組みとしては、今年3月からドッグランを新設したり、ユーザーへの定額プランを定着させるほか、法人向けのキャンププランの提案やカフェ併設の計画なども進めているようです。
“考える”ことを投げかける場所にしたい。社会的価値を見出すことが今後の決め手
一方で、千葉ウシノヒロバは、教育機関や団体と産学連携の活動もおこなっています。それは、“より良い未来を考え、選択するためには、自分たちの視点だけでは足らない”という考えから。
中でも東京大学の“地球からまなび、地球を守る”というコンセプトから生まれた、100年後の地球のために貢献できる”地球医”を目指すプロジェクト「One Earth Guardians育成プログラム」と共に取り組みを続けています。
「最初は議論をする人たちを増やしていきたいという思いからでした。学生さんたちと議論を深めると、今までなかった視点も多く、毎回学びはとても多いです。ただ、100年後の酪農については、話せば話すほど明るい未来が描きづらい。そこで見えてきたシナリオの中で、僕らはどう選択して何ができるのかを話してきました。」
「育成牧場としては、この先千葉県内の農家さんの数を増やすことは難しく、減っていく流れを受け入れていくしかないと考えています。将来的にはメガファームだけになる未来もあり得ることです。そうなった時に、千葉の個人酪農家さんたちの歴史は残ることがありません。ウシノヒロバに預けてくださっていた個人酪農家さんの中にも廃業された方が何人かいらっしゃいますが、皆さんSNSもしていない。そんな方々の実績を残すことも、僕らがやる意味なのかなと思っています。」
前身の千葉市乳牛育成牧場から千葉ウシノヒロバに至るまで50年以上、千葉の酪農家たちから預かった子牛たちはここで育成されてきました。ここは、千葉の酪農の歴史でもあるのです。
川上さんの話を聞いていると、一貫して“社会のため”という視点があることに気づきます。お客さんのため、自分たちのため、そして何より社会のためになることかどうかが、川上さんの判断する際の大きな決め手となるようです。
さらに、川上さんはこう話します。
「社会全体でどう仕組みを考えていくか、僕は“考える”ことが大切だと思っています。社会へ投げかけ、議論する人たちを増やしていきたい。ウシノヒロバは、キャンプを楽しみに来ているお客さんに対して投げかけるための機能でもあります。そのためにオンラインでファンを作ってひとりでも多くのお客さんを呼ぶことや、子牛の里親サービスなど、牛に関するさまざまなサービスを開発していくことも必要だと考えています。」
今年、千葉ウシノヒロバは、「ソーシャルプロダクツ・アワード2025」を受賞しました。
持続可能な社会の実現につながる優れた「ソーシャルプロダクツ」に光をあてた評価制度です。これも、こうした持続可能な酪農の実現に向けた取り組みが評価されてのことだと思います。
事業継続を考える上でのヒントは、畜産事業を別事業との両輪で回すこと、さらに社会へどのような価値を提供していきたいかを考える中にあるのかもしれません。