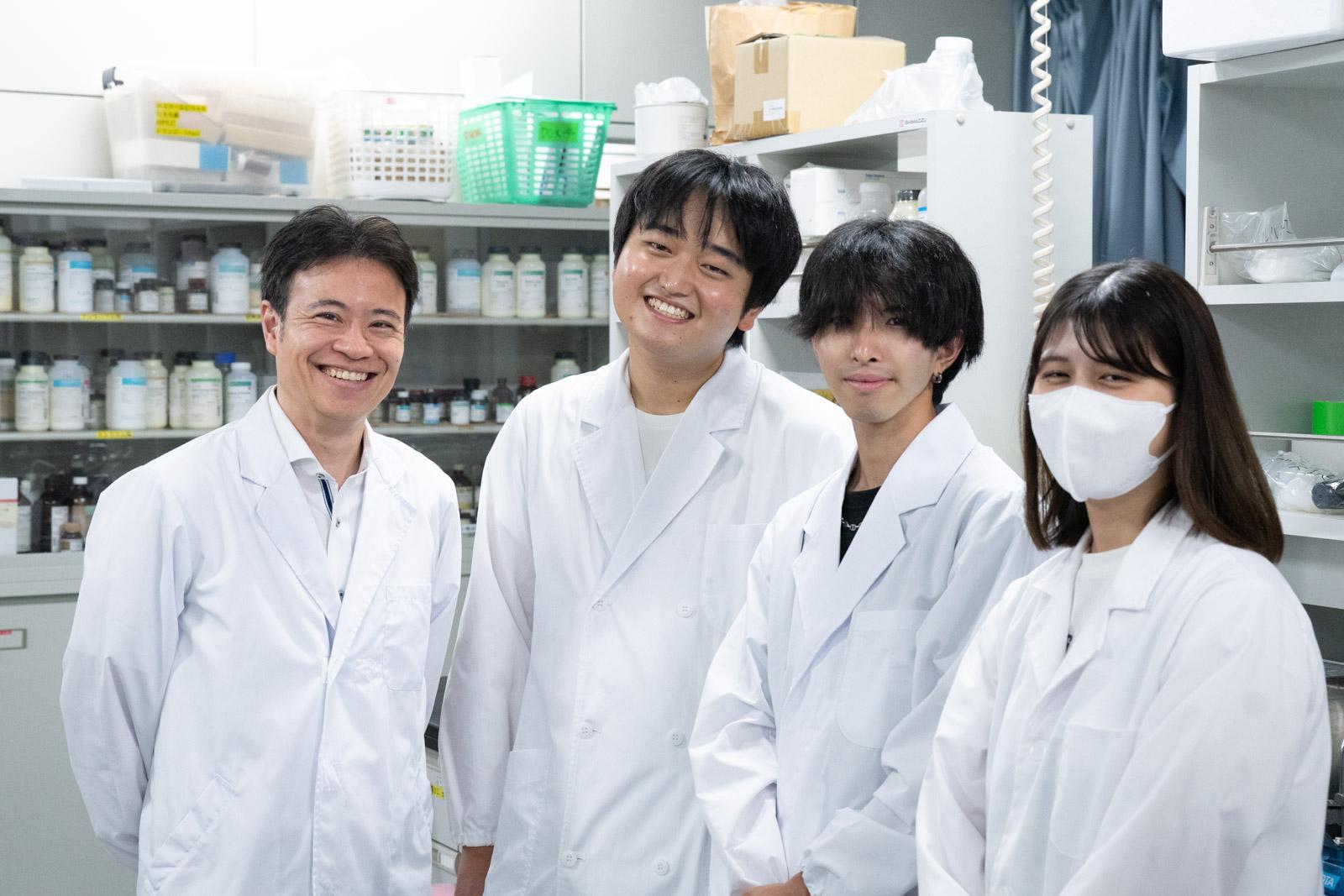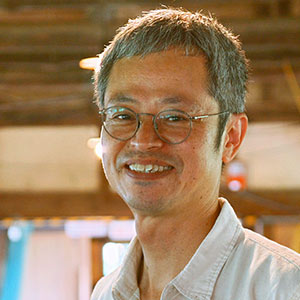日本獣医生命科学大学は、畜産にまつわる知的好奇心を満たしてくれるユニークな研究室が人気
 " alt="">
" alt="">
JR中央線・武蔵境駅より徒歩2分という立地にあり、都内で畜産を学ぶことのできる大学、日本獣医生命科学大学。獣医学部(獣医学科/獣医保健看護学科)と応用生命科学部(動物科学科/食品科学科)の2学部4学科から成り、特色のある実践的な教育と研究を通じて、生命科学の次代の担い手を育成しています。
もくじ

JR中央線「武蔵境駅」からすぐの好立地
日本獣医生命科学大学に通う学生たちにとって、本校の魅力は「多彩な研究室」だと言います。皆さんがどんな研究をしているのか、畜産にまつわる2教室をピックアップし、教授と在学生にお話を伺ってみました。
動物科学科 動物社会科学教室 (システム経営学分野)
畜産のあらゆる課題を社会科学的にアプローチ

動物社会科学教室の学生のみなさん
ここは生産から販売・消費までの過程をひとつのシステムと捉え、多岐にわたる課題について社会科学的なアプローチを行っている研究室。大学だからこそ手がけられる、ニッチな視点での実験が面白そうです。
研究は主に3つのテーマで取り組んでいます。

1つ目は酪農教育ファーム。酪農教育ファームの認証を受けている大学付属の富士アニマルファームで、今年(2025年)は三鷹市の中学生30名を受け入れる酪農体験を予定しています。事前講義を行い、搾乳や餌寄せ、子牛の哺乳、バター作りまで、さまざまな体験プログラムを準備中です。
2つ目はアニマルウェルフェアの研究。乳牛が快適に暮らせれば生産性が上がり、収益性も上がることを立証するため、以下の実験を行っています。

実験1つ目は、繋ぎ飼いをしている乳牛の大腿部に、糞が固まってできる「鎧」の研究。鎧がよくできる牛とできない牛がいるため、その違いを知るために24時間定点カメラで数頭の牛を映し続け、鎧ができるメカニズムを明らかにしようとしています。

実験2つ目は、牛床の研究。人間でもベッドのマットが硬いほうが好きな人もいれば柔らかいほうが好きな人もいるように、牛はどの柔らかさがもっとも快適と感じるのか、牛床の柔らかさを何段階かで組み替えながら生産性の変化を研究しています。
3つ目は堆肥の有効利用の研究。エアレーションによる牛糞堆肥処理をして作った良質な堆肥をパック詰めにして、現在も無人販売を行っていますが、さらに流通を広げるため、原価を考慮しながらなるべく高く売ることができるシステムを考えています。

「動物関連の大学で社会科学系の部屋を置いている大学は非常に珍しいと思います。もともと我々の研究室は「畜産経営学教室」と言い、昭和40年代前半、日本の高度経済成長とともに畜産が右肩上がりに国をあげて進めていた時代に、畜産経営の安定と振興を目的として誕生しました。研究内容は時代に即しながらも常に生産者さんと顔が見える関係にあり、研究データをフィードバックしています」と小澤壯行教授。
アニマルウェルフェアの研究についても、小澤教授は現場へのフィードバックを前提に進めています。
「アニマルウェルフェアは『ヨーロッパは進んでいて日本は遅れている』と強調されることが多いですが、私は『北風と太陽』と同じだと思っていて、『アニマルウェルフェアやカウコンフォートに傾注するとこれだけ生産性が上がって儲かります』と言うことができれば、農家さんは自然と動きますよね。そのためにも生産性や収益性のデータを集めることが大切だと考えています」
小澤教授から高校生へメッセージ

「大学は教育と研究の場です。人は、自分の知的好奇心が満たされる瞬間が一番面白いんです。時には想定していた結果が出ないこともありますが、それもまた面白い。たとえ失敗であっても、まだ誰もやっていないことを研究するのはとても楽しいです。
私は生産者と共に同じ方向を向いて歩むことができる人が増えてほしいと思っています。動物好きな学生さんはぜひ、日本獣医生命科学大学に学びに来てほしいなと思います」
Q. 在学生の皆さんが日本獣医生命科学大学(以下、日獣)を選んだ理由・ここで学んだことは?

私は小学生の時に、先生が某有名チェーン店のハンバーガーを例に取りながら自給率の話をしてくださったことがきっかけで、食料自給率に興味を持つようになりました。日獣に決めたきっかけは、キャンパスが駅から近くてアクセスがよく、大学付属の富士アニマルファームでの実習があり、私のような畜産についてまったく知らない学生でも一から学べるのではないかと思ったことです。大学では、ミートジャッジング競技会に参加したり、牛好きが集まる「うし活Jr.」のサークル長を勤めさせていただき、生産者さんや関連メーカーの方々にお仕事の魅力を聞かせていただく中で自分のやりたいことを見つけることができました。

原小雪さん(大学4年)
私は祖父がヤギや牛を飼っていて、両親は獣医師で動物病院をしていたので、動物に溢れている環境で育ってきました。私自身も獣医師を目指してきたのですが、大学受験でその夢は叶わず、4歳から続けてきたダンスや音楽の道か、動物の道かで悩み、日獣を選びました。研究室ではアニマルウェルフェアの研究をしています。行動観察をして鎧形成のメカニズムがわかれば、牛にとってより快適な施設を作ることができます。私たちの研究で少しでも農家の方々にアニマルウェルフェアの考え方を広められたらと思っています。

私の実家は両親が酪農ヘルパーをしていたので、幼い頃から酪農家さんのところへ行って牛に触れながら育ち、物心つく頃には、動物関係のお仕事に就きたいと思っていました。専門学校か大学進学かで悩みましたが、高校生の頃はまだ動物関係のお仕事にどんなものがあるかわからなかったので、まずは大学4年間で幅広く学べたらと思って日獣に入りました。担い手不足や飼料の高騰など、生産現場の実態への理解を深める中で、自分の性格には農家さんを支える立場として働くほうが向いているなと考えるようになりました。

私は鹿児島県出身で近くに牧場も多く、親戚が肥育農家をしていたこともあり、皆さんにとっての犬猫が牛というほど、牛が身近な存在でした。日獣は大学付属の富士アニマルファームが酪農教育ファームの認証を受けていると知り、自分も酪農教育活動ができればいいなという気持ちで入りました。今は研究室での学びやうし活Jr.サークルのボランティアで小学生の搾乳体験のお手伝いや酪農家さんのお仕事紹介、食の大切さを話す中で、動物を通じた教育活動を行いたいという気持ちが強くなりました。一方で小さい頃から持っていた動物園の飼育員の夢もまだ諦めず、学芸員の資格を取れるように勉強を頑張っています。
動物科学科 動物栄養学教室

飼料の自給率を持続的に上げる研究
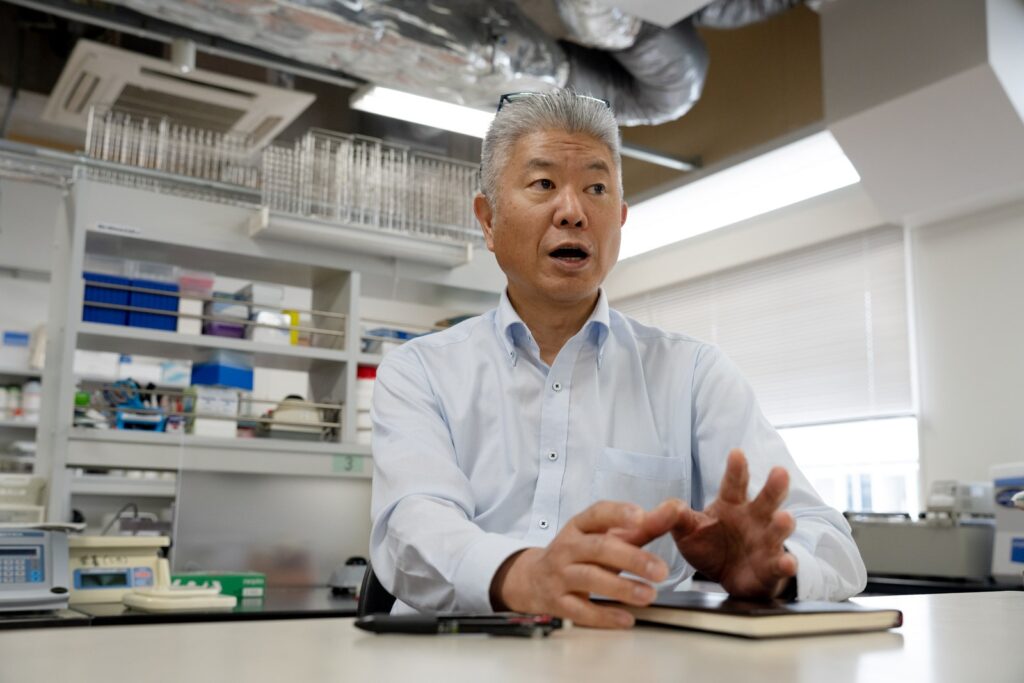
こちらは、黒毛和種の肥育で飼料自給率を持続的に上げる研究を行う研究室。和牛肥育の常識を覆す方法で、コロナ禍以降の社会情勢の影響を大きく受け、飼料価格が高騰する今だからこそ注目の集まる研究です。
柴田昌宏教授は、大学の地元・武蔵境にある、「26K(にーろくけー)ブルワリー」という3坪ほどで営む小さなクラフトビール醸造所と組み、これまで産業廃棄物として有償で処理していた「麦芽かす」を成分分析して飼料化に成功。
通常、約9割を輸入に頼っている穀物の濃厚飼料と牧草の粗飼料を食べる肥育牛ですが、当研究室では、濃厚飼料の代わりに麦芽かすを使った飼料とデントコーンサイレージを多給し、本来草食動物の牛の性質を活かして放牧を取り入れた、経産牛の肥育に取り組んでいます。

これで飼料自給率は6〜7割ほどに上がり、フードロス対策にも繋がります。今秋に出荷が予定されているので、枝肉を分析し、肉質や生産性の向上などの改善点を見つけていく予定だそうです。
ただ、味が美味しかったとしても赤身肉は現行の枝肉評価制度では高い評価が得られないため、独自の流通を持つことが、収益増の鍵を握ります。だからこそ、『国内飼料を有効的に使っている』『経産牛である』といった生産ストーリーに共感してもらい、値段に納得して買ってもらうことが、今後の課題でもあるようです。
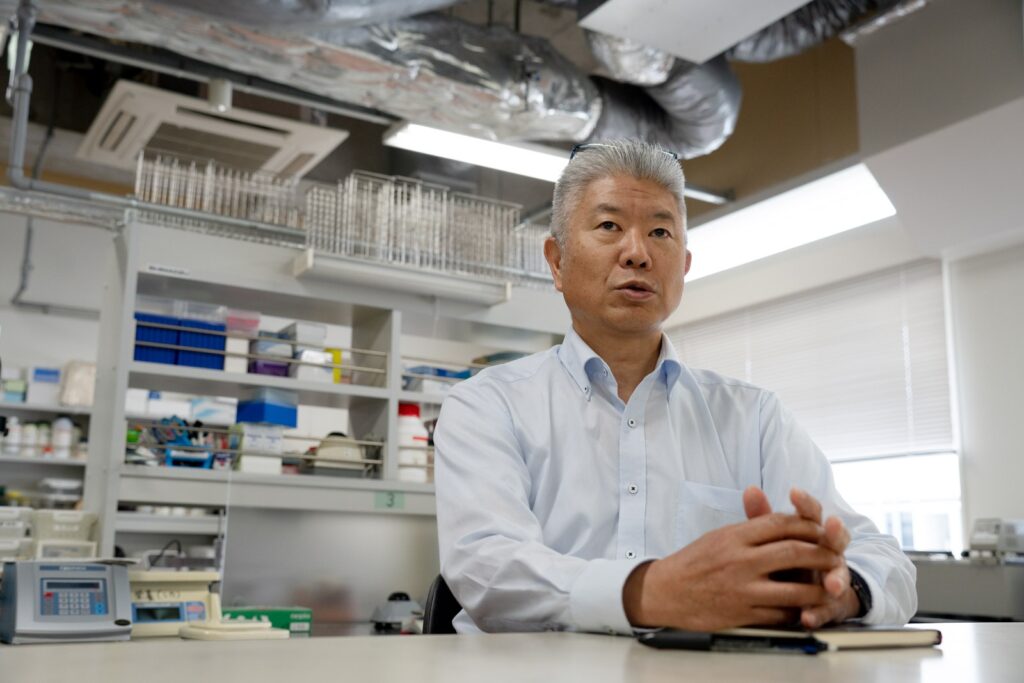
「農研機構でも去勢牛の肥育において濃厚飼料を多給せず、放牧などを利用して粗飼料を主体とした飼料設計の研究を行っていました。もちろん播種して肥育用の草地を整えた上で、牛に食べさせるための工夫は必要ですが、これらの飼料でも和牛としてのポテンシャルはあるので、通常の肥育牛と大きさはほとんど変わらないくらいに仕上がるんです。
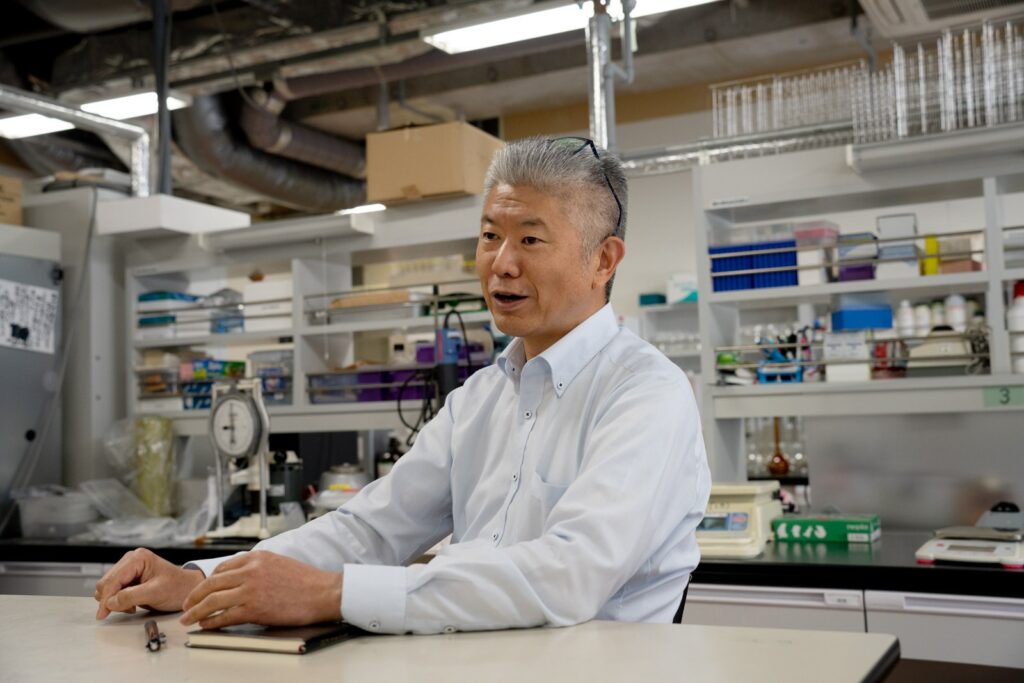
一般の方々の中には『A5ランク=高級な肉』という認識がありますが、実は今は血統の改良により、和牛10頭のうち9頭が霜降り肉になります。そう考えると、高脂肪交雑(サシが入った)の牛肉は世の中に溢れていて、逆に赤身肉のほうが希少と言えます。
私が手がける肥育は、A5ランクの肉は目指しません。大学に来た当初はこの常識外な肥育方法に周りの教員たちからも驚かれましたが、味の面でも、シェフの方から『濃くて旨味が強い』という評価をいただき、リピーターになってくれている顧客もいます。
通常の肥育と比べて何か特徴的な点があれば、それを販売のプロモーションに使うこともできます。今はどのブランド牛も同じような飼料で育てていて牛肉の多様性が失われていますから、生産のストーリーだけでなく、肉そのものの差別化に繋げられると考えています」
柴田教授から高校生へメッセージ
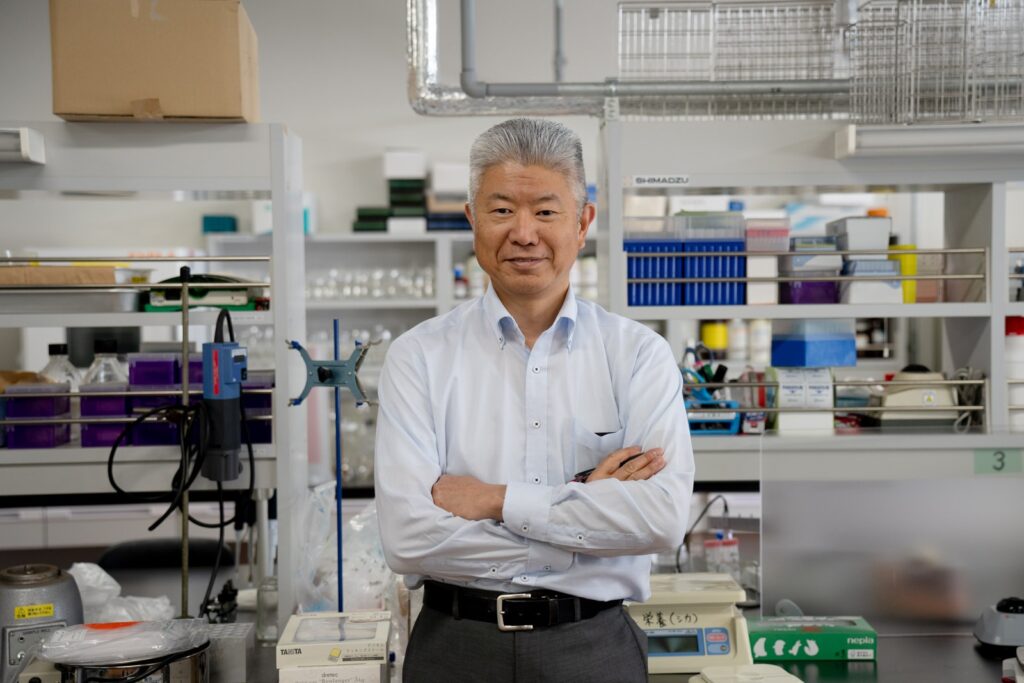
「最近でこそSDGsということが声高に言われていますが、国産飼料で、草食獣としての牛の機能をフルに活用して牛肉を作ることができないかという研究を、僕らは15年ほど前から続けてきました。オープンキャンパスで研究室の取り組みを紹介すると、この研究室に入りたいと受験して僕の研究室に来てくれる子たちが毎年います。『飼料自給率を上げて、牛の本来の機能を活用した生産』、『牛に優しい』、『環境に優しい』といったキーワードが、今の学生の皆さんには響くのではないかと思っています」
Q. 在学生の皆さんが日獣を選んだ理由・ここで学んだことは?

私は実家が乳牛の経営をしていて動物と距離が近かったので、動物系の大学に入りたいなと思って受験しました。高校生の頃、毒素のある魚を食べた魚や動物はその毒素を体の中に溜め込んでしまう悪い循環があるという話を聞いたことがあり、それは私たちが食べるお肉にも当てはまるのではないかと思って家畜の餌にも興味があったので、この研究室に入りました。麦芽かすを使って自分たちが用意した餌を実際にあげ、最初は食いつきが悪かった牛がだんだん食べるようになってくれた時はとても嬉しかったです。

私は昔から動物が好きだったことが理由で日獣に入りました。大学2年の時に牧場でバイトしていた友だちが共進会の手伝いに行くのに付いて行き、私も牛が大好きになり、3年から選択する研究室は、牛の研究ができることと、付属の大学牧場にどの研究室より多く行けるということでここを選びました。高校生の頃はまったく想像もしていなかった未来ですが、月に2回ほど、1週間くらい泊まり込みで研究するので、ずっと牛が見られることも嬉しいですし、同じ草でも水分や栄養素成分が結構違っていて、飼料の分析をするのも面白いです。

私は神奈川県の相原高校の畜産学科出身で、畜産や動物に関わる道に進みたいと思って、専門学校と大学とで悩んだ上で日獣を選びました。まだやりたいことがはっきりしていないし、知らない仕事もあるかもしれないので幅広く学んでみたいという思いがあったからです。この研究室には、富士アニマルファームに行けることと、柴田先生の栄養学の授業が興味深かったため、入りました。大学2、3年の夏休みに学校で募集していたインターンで畜産物の輸入に関する検疫業務を体験したことがきっかけで、今は農業系の公務員試験を受けています。

動物が好きだったことと家から大学が近かったという理由で日獣を選びました。元々は犬猫に興味があったのですが、大学に入ると実家が畜産を営んでいる人がいたり、授業で家畜のことを学んだり、実習で富士アニマルファームに行ったりするうちに、牛が好きになりました。研究室は見学に行った時に先輩たちが先生とも仲が良く、楽しそうな雰囲気が良くてここに決めました。同級生たちと過ごす大学生活は、とても楽しいです。

大学に入るまで畜産にまつわる仕事のことはほとんど知りませんでしたが、研究室で行う肉質の成分分析などの実験は、想像以上に面白く、自分に向いているのかもしれないなと思いました。ずっと動物園の飼育員がしたいと思っていましたが、今は牧場での産業動物の飼養管理などの仕事も視野に入れて考えています。高校生の頃には触れたことのないようなことを大学で学ぶうちに、自分の興味の幅も広がりました。

■大学情報
日本獣医生命科学大学
〒180-8602東京都武蔵野市境南町1-7-1
TEL:0422-31-4151